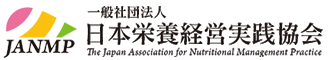 |
お問い合わせ | 資料請求 |
|
JSPEN2025
栄養経営士 発表者コメント
口演41 摂食嚥下障害2
認知症高齢者の丸飲み嚥下に対するソフト食裏ごしの取り組み
~機能が低下しても食べる喜びを感じる食支援~

南浜中央病院 栄養科
熊谷 弘美さん
認知症患者は年々、増加傾向にあります。認知症の進行とともにソフト食へ移行する患者が多く、口腔内にため込み嚥下が困難になってくると、更にゼリーを裏ごししています。裏ごしの患者はその機能や栄養状態を何年も維持している症例が多いということが分かってきました。
当院で10年以上前から取り組んでいるソフト食の裏ごしを、学会発表という場で形にしてみたいと思いました。6分の発表時間内にまとめるのは大変でしたが、ソフト食(原形と裏ごし)の写真やグラフを使用し、誰が見ても分かりやすくを心掛けました。
今年は摂食嚥下専門療法士資格の更新の年にあたり、また新たな気持ちで摂食嚥下に取り組んでいきたいと思いました。
要望演題07 摂食・嚥下障害に対する栄養治療
嚥下調整食の共通理解にむけた国際嚥下食標準化構想(IDDSI)活用の試み

旭川赤十字病院 医療技術部 栄養課
長瀬 まりさん
国際嚥下食標準化構想(IDDSI)の活用に向け、当院での臨床栄養学実習の一部に取り入れた試みについて報告しました。これまで摂食嚥下がテーマのNST研修会開催などをおこない、嚥下調整食の共通理解に向けた取り組みをおこなってきました。
IDDSIでは、フォーク押しテストではかたさと粒の大きさを評価し、スプーン傾けテストで付着性を評価します。身近にあるもので食品の物性を評価ができるため、調理師や在宅で調理を担う方にも活用していたけると考えます。適切な評価にむけて広げていきたいと思っています。
◎合同パネルディスカッション09(日本褥瘡学会) 褥瘡対策と栄養療法の連携
褥瘡予防における栄養管理の役割と地域連携による栄養介入の重要性

東葛クリニック認定栄養ケア・ステーション松戸(機能強化型)
髙﨑 美幸さん
今回は、褥瘡予防における栄養管理と多職種連携の重要性について発表しました。質疑応答で「DESIGNの各ステージで必要な栄養素」について質問を受けましたが、十分に答えられず、後日オンデマンド配信時にコメント追加を提案したものの叶わず、自身の準備不足を痛感しました。
一方で、シンポジストの先生方と具体的な事例や成果を共有できたことは非常に有意義でした。多くの質問や意見をいただき、褥瘡管理における栄養士としての役割を再認識する機会となりました。今後は専門知識と実践力をさらに高めていきたいと感じました。
パネルディスカッション08 【アンサーパッドセッション】上質な栄養ケアに向けたNSTと病棟配置管理栄養士の役割と展望
病棟配置とNST連携で目指す上質な栄養ケア

東京医科大学病院 栄養管理科
福勢 麻結子さん
当院では管理栄養士が全病棟に配置されており、毎日多職種と協力をしながら栄養ケアに取り組んでいますが、NSTと病棟管理栄養士がどのように共存し、上質な栄養ケアに取り組んでいくかということを考えさせられました。
かつてのNSTは全科型・週1回の活動が一般的でしたが、時代ととも求められているチーム医療は変化しているように思います。本セッションを通して、「病棟管理栄養士は栄養サポートの質の向上・均一化を目指し、それをサポートするNST」という形を追求していきたいと感じました。
パネルディスカッション09 改めてERASを考える:術前飲料の摂取について議論してみよう
整形外科手術における術前アミノ酸・炭水化物負荷飲料の効果

手稲渓仁会病院 栄養部
入江 翠さん
整形外科での術前飲料導入の効果について発表させていただきました。コメディカルからの発信で、多職種で連携しながら術前飲料を安全に導入できたことを、聴講して下さった方々に伝わっていましたら幸いです。大変緊張しましたが、ディスカッションでは、日本の医療でのこれからのERASについて、座長の先生や他のパネリストの先生のお話を拝聴し、大変勉強になりました。
今後も食を通じて患者さんの身体の回復の支援を図ること、そして食事が患者さんの癒やしとなるよう、力を尽くしたいと感じました。
口演03 集中治療
重症患者のGLIM基準による栄養評価と予後との関連

上尾中央総合病院 栄養科
寺田 師さん
ICUへの管理栄養士常駐開始から継続しているGLIM基準による栄養評価を集積し、発表させていただきました。重症患者の栄養評価を行うにあたり、身長・体重・通常時体重・筋肉量の評価について発表での紹介やフロア、座長の宮澤先生からのご質問で皆さんと共有できました。
個人的な考えではありますが、管理栄養士は栄養評価の専門家として、実臨床で通常時体重が分からない場合は、病歴や生活歴、身体状況から体重推移を推論することも必要と考えます
第2回 患者さんのための見た目にもおいしい病院食コンテスト
グランプリ講演

武蔵野徳洲会病院 栄養管理室
土屋 輝幸さん
患者の元へ食事が行き届くまで、数多な人手と時間が導入されています。そこには妥協がなく、患者のためにという想い一心で真摯に向き合う栄養の専門職がおります。給食管理は立派な栄養管理の根源であり、専門性の高い業務です。昨今、求められている栄養管理と給食管理を両立しながら、患者サポートをしていけるように、多くの聴講者に伝われば幸甚に存じます。
口演39 栄養指導
三位一体の多職種連携がこども食堂にもたらした公衆衛生的栄養教育
医療機関が運営するこども食堂は、大変稀であります。またその中でも差別化を図るために、昨今のトレンドである三位一体に着目しました。病院は、専門職の集合体であるため、歯科医師・理学療法士等との連携が容易であり、それぞれの専門性を活かして、こども達へのアプローチが出来ました。
利用してくださるこども達が成長していく姿を糧としながら、今後も永続的な運営をしていきたいと考えております。
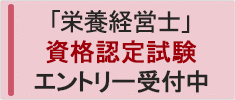
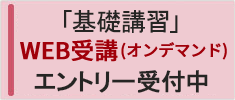
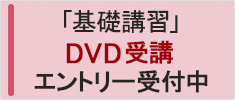


口演04 栄養評価1
当院におけるMUSTとGLIM基準の実践と導入後の課題
仙台市立病院 栄養管理科
佐々木 麻友さん
MUST/GLIMを運用する中で、過小評価の要因として教育不足があると再認識しました。当院では看護師が評価を行っていますが、多人数に正しい方法をどう伝え、実践に落とし込むかが課題です。
発表後、同じ電子カルテシステムを使用し、MUST/GLIMを導入予定の施設の方から具体的な運用について質問を受けました。導入に向けた課題を共有でき、大変有意義でした。
MUST/GLIM導入にあたっては「栄養管理の成果をもって施設経営の一翼を担う」など栄養経営士の視点が役立ちました。今後もマネジメントスキルを活かし、評価の精度向上と栄養介入の質の向上を目指します。