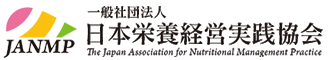 |
お問い合わせ | 資料請求 |
|
第40回日本栄養治療学会学術大会 JSPEN2025| 2025年2月
日本最大の臨床栄養の大会で多数の
栄養経営士が登壇、グランプリ受賞も(1)
2025年2月14、15日の2日間、JSPEN2025がパシフィコ横浜ノース/アネックスホールで開催された。「栄養治療の船出」をテーマに行われた大会では本協会の理事や会員が多数登壇、病院食コンテストでは土屋輝幸さんが二冠を達成するなど、各所で栄養経営士が活躍を見せた。簡単ではあるが、大舞台で発表した栄養経営士の勇姿を紹介する。
■1日目
開会式のあと、朝9時から一斉に各会場でプログラムが始まりました。第5会場では「第2回患者さんのための見た目にもおいしい病院食コンテストグランプリ講演」があり、クックサーブ部門で土屋輝幸さん(武蔵野徳洲会病院)が2年連続でグランプリを受賞、連覇を達成しました。
グランプリ講演で土屋さんは「おいしい食事の提供は管理栄養士の専門性を活かせるゆるぎない業務であると考える。食事は病院の顔にもなり、栄養は患者さんの笑顔につながる。こうしたコンテストが病院給食の活性化につながることを願っており、またそこに自分も貢献したいと思う」と語りました。
さらに土屋さんはクックチル部門でも準グランプリを獲得し、両部門で表彰台に上るという快挙を成し遂げました。

宮澤靖代表理事(東京医科大学病院)が座長を務めた口演03「集中治療」では寺田師さん(上尾中央総合病院)が「重症患者のGLIM基準による栄養評価と予後との関連」のテーマで登壇。GLIM基準で判定するとICU・CCU入院患者の3割弱が低栄養であり、重度低栄養患者は予後不良が認められたと自院で行った調査結果を報告しました。

シンポジウム01「GLIM基準を日本医療企画の医療現場に定着させよう」では西岡心大理事(長崎リハビリテーション病院)が登壇し「栄養スクリーニングツールの妥当性と使用の現状」をテーマに発表しました。西岡理事はさまざまなスクリーニングツールを紹介し、自身が行った検証の結果を報告しながら、適切なツールの使用のためには各ツールの妥当性の検証が重要だと説きました。
口演04「栄養評価1」では佐々木麻友さん(仙台市立病院)が「当院におけるMUSTとGLIM基準の実践と導入後の課題」で発表。自院で電子カルテにMUSTとGLIMを導入して運用を開始し、低栄養患者を適切に評価するための運用について検討した結果と、今後につなげるための課題について報告しました。
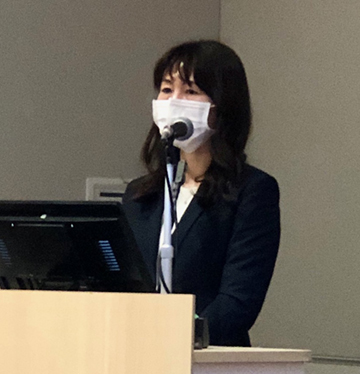
口演05「栄養評価2」では「GLIM基準と従来法による栄養評価結果の比較」というテーマで森本聖子さん(姫路中央病院)が登壇しました。従来法として血清アルブミン値による評価を使用、GLIM基準による栄養評価と比較し、GLIMの方が包括的な栄養評価が可能であると結論づけました。

要望演題07「摂食・嚥下障害に関する栄養治療」では長瀬まりさん(旭川赤十字病院)が「嚥下調整食の共通理解にむけた国際嚥下食標準化構想(IDDSI)活用の試み」を発表しました。日本では嚥下調整食学会分類2021が主流ですが、IDDSIはフォークとスプーンがあればテストができるため簡便で評価がしやすい等のメリットがあり、いずれは患者とその家族による活用を目指したいと展望を語りました。
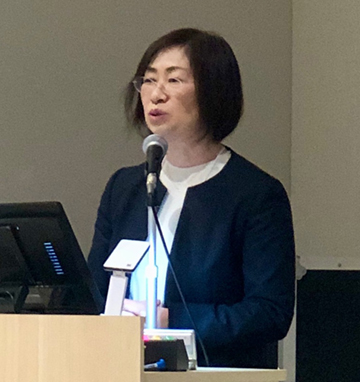
ワークショップ07「口腔・栄養・リハビリテーションの一体的取り組みへのエビデンス構築」では宮島功さん(近森病院)が登壇し「リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算算定に向けた一体的取り組みと実践」について発表しました。自院での多職種連携による取り組み状況を紹介し、算定件数についても報告しました。
西岡心大理事が座長を務めた口演06「地域連携在宅栄養・在宅NST」では「学校および学校医との連携により栄養・心身状態の改善を認めた心因性食欲不振症(AN)の一例」と題して森ひろみさん(杏クリニック)が登壇しました。本人・家族とも摂食障害と認識していなかった16歳・女子に対し血液検査と身体所見からANと診断、栄養指導を行って改善した例を紹介しました。これは学校と学校医であるクリニックとの迅速な連携が功を奏した事例であり、今後は地域医療における柔軟な栄養相談窓口の体制構築が課題であると語りました。
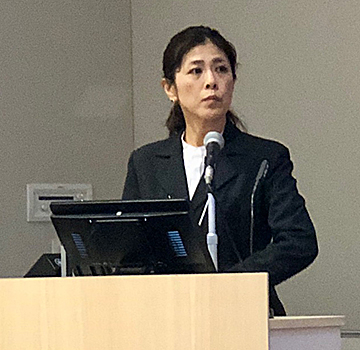
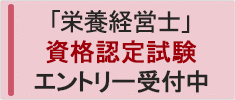
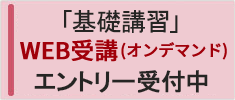
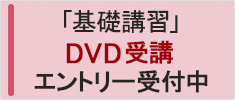


ポスター発表(1日目)
01「栄養指導」
「術後二次性のサルコペニア患者に対して外来栄養指導を行い改善を認めた1症例」
本荘真一さん(別府医療センター)
04「集中治療3」
「集中治療室における早期栄養介入経口摂取への取り組み」
山本純子さん(彩の国東大宮メディカルセンター)
16「がん(胃・食堂)2」
「胃切後胃癌患者の『最適化栄養食』喫食前後の栄養摂取量についての検討」
梶原克美さん(近畿大学病院)
32「小児・重度心身障害」
「発達障害児に対し、STと管理栄養士が連携したことにより体重増加不良が改善した1症例」
小林弘治さん(日本心身障害児協会島田療育センター)