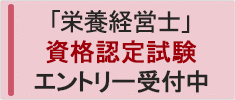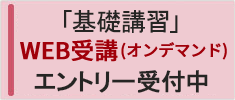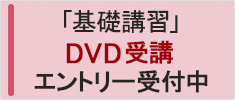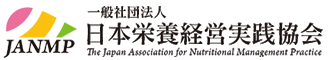 |
お問い合わせ | 資料請求 |
|
令和6年能登半島地震 被災報告| 2024年11・12月
非常時を乗り切るのに必要なのは
臨機応変に対応する力(1)
令和6年能登半島地震(令和6年1月1日発生)で被災し、DMATの拠点にもなった公立能登総合病院の栄養部には2名の栄養経営士が在籍している。その、江成雅美さんと栄養士長である町駒珠美さんに、震災発生からの動きや対応についてうかがった。
長期断水でも患者のため3食提供し続けた
公立能登総合病院は石川県七尾市にあり、中核病院として地域医療に貢献している。栄養部は管理栄養士6名、栄養士2名、調理師11名(会計年度任用職員含む)、調理員11名、栄養事務1名という体制をとっており、基本的に管理栄養士が病棟を、栄養士が厨房を担当している。給食は直営で下膳と洗浄のみ外部に委託。病床数は全部で434床だが、病棟編成の見直し等があり、現在は1日約700~750食を提供している。
震災当日はお正月でもっとも入院患者が少ない日であり、院内にいた管理栄養士は町駒さんひとりで、あとは厨房に7名スタッフがいたのみだった。
「地震があったのは16時10分で、厨房ではベルトコンベアで盛り付けをしようと準備していたところでした。温冷配膳車が1メートルほど移動する大きな揺れが起き、スタッフが慌てて食材の入っているラックを押さえ、食材は廃棄せずにすみました。しかし、地震の影響で院内のエレベータが止まり、貯水槽が破損、漏水し、水も止まりました」(町駒さん)


震災から20分ほどで、院内に対策本部が設置された。七尾市内は断水状態で病院のエレベータは全基停止、暖房も止まり、ヘリポートの一部が崩落、そのほかも多数の被害があったそうだ。
エレベータが使えないため災害対策本部に配膳を依頼し、看護師やリハビリ職員の協力のもと19時頃に配膳が完了。調理師が気を利かせて栄養部スタッフ全員の安否を確認し、召集前に1名が登院して作業に加わった。下膳・残食の片付けは、委託企業が出勤停止の指示を出したため、21時頃までかけて調理師が行った。
町駒さんはスタッフとともに下膳や割れた食器の片付け、調理機器の点検、保存水と備蓄米の搬入等を行ったあと、給食を止めないために翌日からの献立作成に取り掛かった。お正月用の食材があったためそちらを優先して消費できる献立をつくり、翌朝の献立、材料の調整が終わったときには22時過ぎになっていたそうだ。
「揺れで落ちた棚の物は元に戻すだけで済みましたが、断水でコンベクションオーブン、回転釜、食器洗浄機が使用できなくなりました。ガスも安全が確認できなかったので、IH だけで調理しました」(町駒さん)
業者による厨房機器の点検は1月3日には行われたものの、断水と故障で、2台あるオーブンのうち1台は栄養部の断水が終わった2月1日まで、もう1台は故障して3月まで使えなかったそうだ。こうした「使える厨房機器に制限がある場合」の対応も考えておくと安心かもしれない。


水が使えず使い捨ての食器類、衛生ゴミが大量に発生
震災直後から水が止まっていたので、食材・調理器具・食器の洗浄が行えず、食事は備蓄米、ローリングストック食品、自然解凍で食べられるものを、食器はディスポを使用して給食提供を行った。手洗いも頻回にはできないので使い捨ての手袋を使用。ディスポ食器や衛生ゴミが入ったポリ袋が大量に出ることとなった。
震災翌日からは週に何回か自衛隊の給水車が来たが、真冬に水を汲んで運ぶ作業はとてもきつかったという。
「給水車の水をポリタンクに入れて保存し、備蓄水のペットボトルが空になったらそこに入れて使いました。ポリタンクは大きなものよりも、蛇口がついているもののほうが役に立ちました」(町駒さん)
ポリタンクの水や支援物資は、置き場がなくなり廊下等にも置くことになった。
結局、水道が復旧したのは栄養部が1月末ごろ、病院全体では2月に入ってからだった。なお、断水中は透析治療が行えないため透析患者は転院し、その間、透析食は出なくなった。